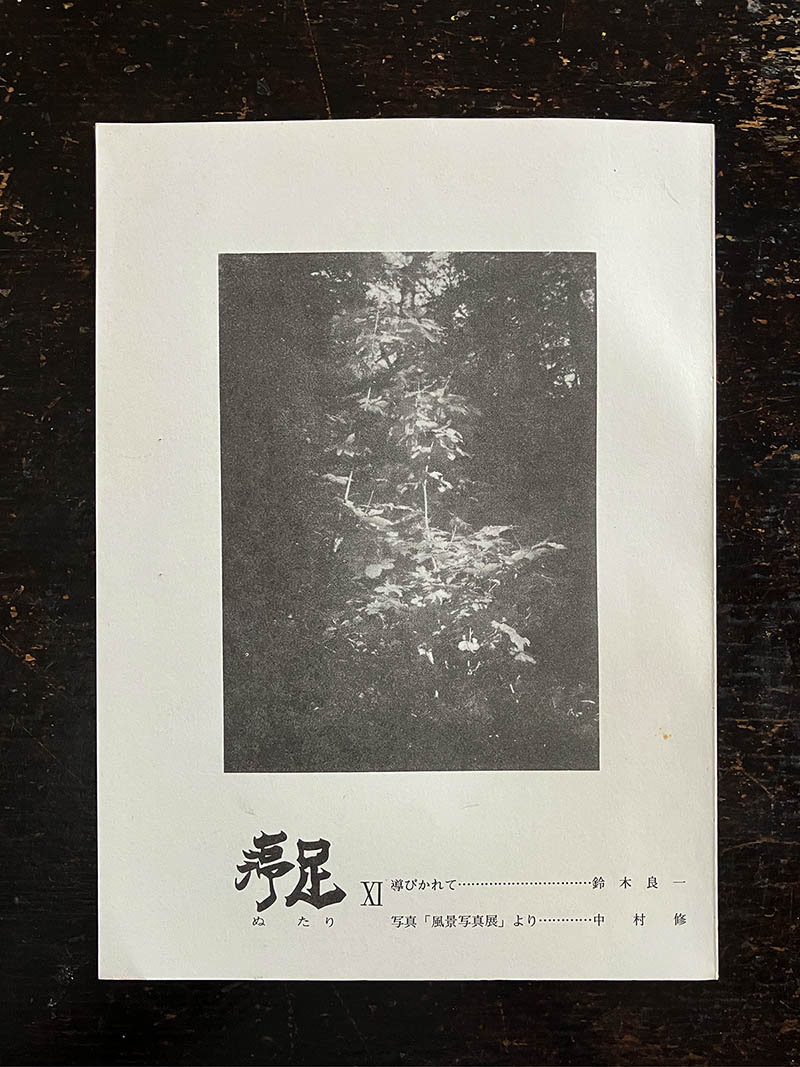腐植土

かつて繁栄を極めたメソポタミア文明は土が砂漠化したことで衰退したと言われています。世界では今も地球温暖化などの影響で砂漠化が進んでいる地域があり、その一方で各地で極端な豪雨災害が頻発したりしています。昨2024年から今年にかけての山火事が頻発したのも温暖化の影響だと言われています。
岩石が風化してできた砂や粘土だけでは土とは言えません。長い時間をかけて動植物などが分解されて混じったものが土です。土の中にはさまざまな種類の細菌が存在しています。その細菌が死んだ動物や昆虫、落ちてきた葉っぱなどを分解し腐植土となります。腐植土はさまざまな養分も含み、保水性や通気性もあり、植物が育つためにはなくてはならないものです。
水害などで削り取られてしまった表土が再生するには数十年から数百年という時間がかかります。私の育った地域では養分を多く含む黒土の土地がたくさんありました。南魚沼の八色スイカを栽培している畑の土も黒土です。そのおかげで大きくて糖度の高いスイカが実ります。どちらかというと雪が多かったり、湿度が高い地域に良い土ができるのではないかと思います。子供のころに畑で遊んでいると黒っぽい土のせいで服が真っ黒になったものでした。
魚沼米が美味しいのは豊かな土のおかげだと考えられますが、現代の農業ではたくさんの肥料を使い、小規模農家ではコストがかかりすぎるため生産を維持していくのが大変なのかもしれません。ウクライナの戦争の問題も価格高騰の原因の一つと言われています。
2009年に開催された1回目の「水と土の芸術祭」では各地の地層の標本を作っていました。この写真は秋葉区の石油が染み出す地層がある標本を剥ぎ取る作業です。地層標本の中には石炭のように炭化した木の枝も含まれていて、子供の頃に考古学者になりたいと思っていた私にとってはなかなか興味深い作業でした。