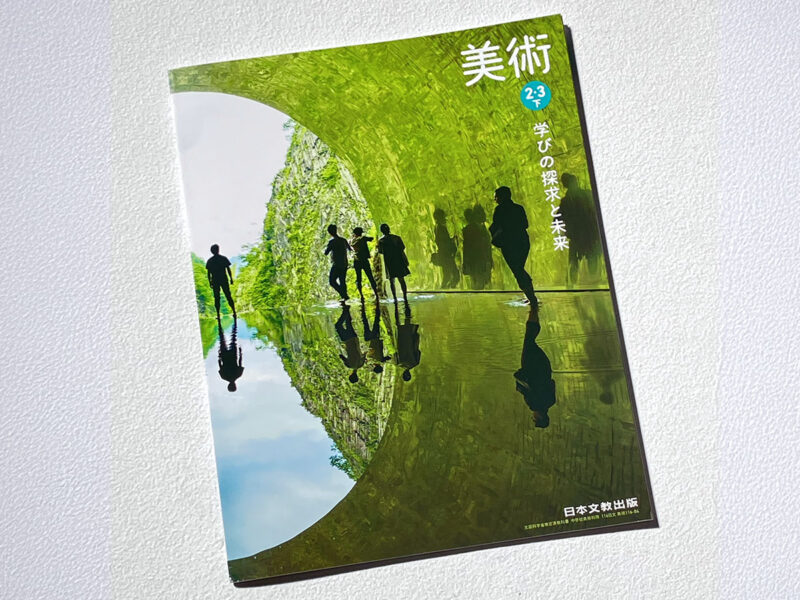豊穣の木

5歳か6歳の頃に家出をしたことがあります。
といっても、あまり行動半径が広くなかった子供のころのこと、家の裏にある土手の桜並木の老木の一つに束ねて立てかけてあるはさ木の陰に隠れていました。暗くなり始めた夕暮れ時、桜の根元に寄り添い、恐怖と不安の中、息を潜めていたことをよく覚えています。
古木の思い出をひとつ。母親の実家近くにある寺の参道階段脇には桂の大木があります。長尾景虎を頼って越後に落ち延びた上杉憲政の家臣、大石綱資の嫡男綱元が天正11年(1583年)に創建したこの寺に植えたと伝えられています。日本神話では神の使者が地上を訪れるとき、桂の木に降りるという。参道入り口は神の国と村を結ぶ場所であり、訪れた村人に天の恵みを授ける象徴として桂を植えたのかもしれません。ちなみに集落の名前は大石性に由来すると思われます。
ヨーロッパでいうと、神聖な木とされている菩提樹に近いような気がします。菩提樹は愛と優しさのシンボル。樹種は違いますが、葉の形はどちらもハート形、子どもとよく遊び、とびきり優しい笑顔だった住職の印象と重なって懐かしさが込み上げてきます。

(写真は桂の古木。昔はお香にするために寺に植えることが多かった。寺の縁起によると樹齢は400年以上)
桂の古木は、根元を流れる幅一間弱の沢がコンクリートで覆われてからは樹勢が衰えましたが、いまだに春になるとたくさんの葉を付け、そのさまは豊穣そのものです。
村や参道前の風景は変わりましたが、今でも存在感のある桂の木を見上げると、沢でイモリやサワガニを捕まえたりハートの葉で遊んでいたころの豊かな記憶がよみがえってきます。
桂は村を見渡す辻にあり、数百年にわたって人々の生活や往来を見守ってきました。同郷の歌人、宮柊二は〈わが生に関りありし河岸のかのよろんがしは今無しといふ〉と歌いました。「よろんがし」とは? 樹木の種類が何なのか調べても判然としませんでしたが、歌人にとっても過去の人との記憶や思い出を寄せる樹木。「寄らん樫」で良いのではないかと私は勝手に推察しています。この短歌は宮柊二が生まれ、育てた原風景の一つが、魚野川河岸の一本の樹木であったのでしょうか。
宮柊二が回想して歌った「よろんがし」は言うに及ばず、私が家出した時にお世話になった裏の土手の桜の木も、もはやごつごつした幹の手触りの記憶の中にしか残っていません。村の歴史とともに歩んできた寺は跡継ぎが絶え、桂の守り手もいなくなりました。移ろう無常さを歌うにしても、あまりにも早い変わり方です。
厳しい雪国の気候に耐え、私が生まれるよりはるか昔より根を張って生きてきた樹木は、人格を持つ存在として現在の私の写真の中に象徴的に登場しているような気がしています。かろうじて残っている桂の老木は、美しい葉をたくさん広げ、しばらく会いに行かなかった私を歓迎してくれていました。