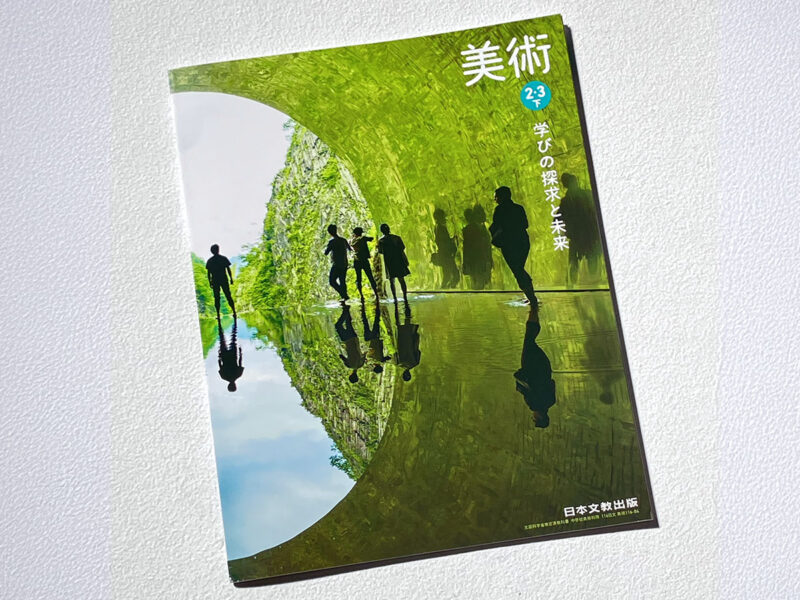鈴木良一「導かれて」
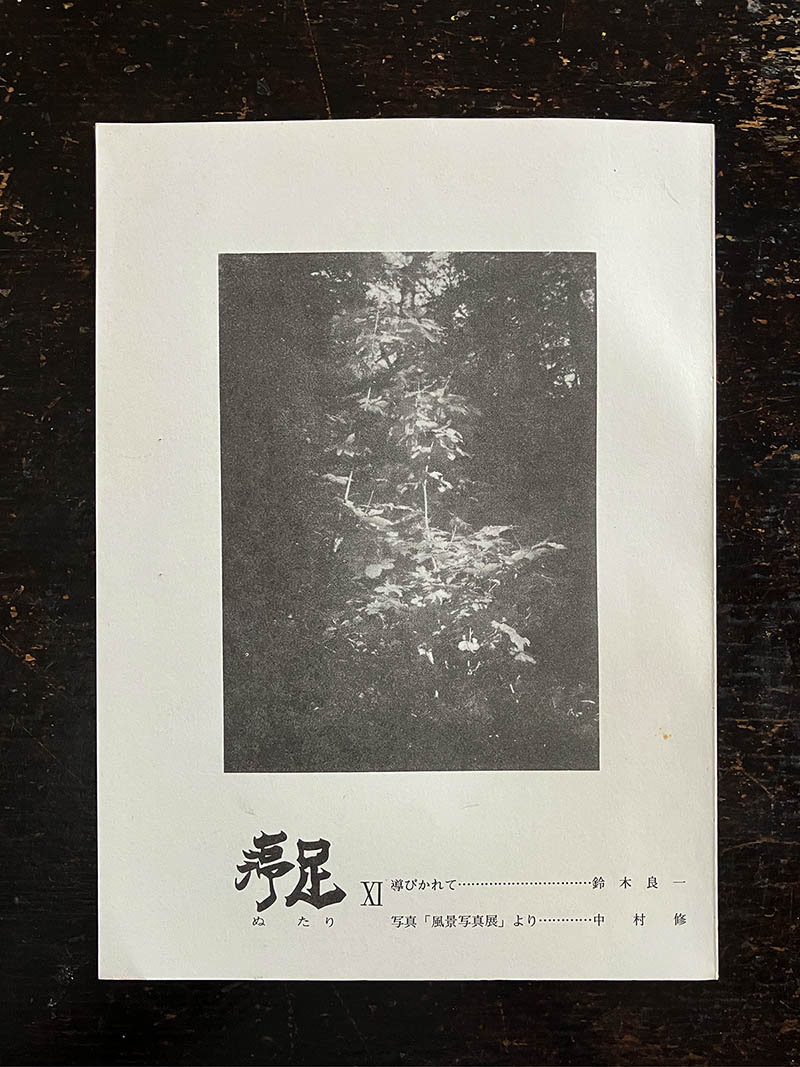
1986年4月、私は古町の北陸ガスホールのギャラリーで初めての展覧会を開くことになった。とはいえ、このギャラリーはもともと別の用途で使われていた空きスペースで、声をかけていただき、使わせてもらえることになった場所だった。前年、尾瀬の山小屋で「尾瀬」という小さな写真展を開いてから、まだ一年も経っていない時期のことだ。きっかけははっきり覚えていないが、会場隣の「ライフ」が閉館した後、市民映画館「シネ・ウィンド」の設立に関わっていた「ライフ」最後の支配人さんから紹介されたのかもしれない。当時私は映画にそれほど詳しくなかったが、知人のコピーライターに誘われ、シネ・ウィンドのオープニングメンバーに加わっていた。フリーランスになって間もなく、仕事も少し忙しかったため、新たに撮影する余裕もなく、山登りなどの折々に撮りためていた風景写真で構成しようと考えていた。

(現在ギャラリーは閉鎖したが、左が北陸ガスホール、右にあったのが旧名画座ライフ。古町7番町)
そんな折、やはりシネ・ウィンドに関わっていた詩人の鈴木良一さんに相談した。私は、基本的に声がかかったことは断らないという、フリーランスになりたての自分の姿勢に従っただけだったので、会期が迫る中、後付けでどうテーマを設定するか悩みつつ、鈴木さんに自分の思いを伝えた。
展覧会のタイトルは『「風のある風景」写真展』とした。シネ・ウィンドにちなんだわけではないが、静止した風景写真に動きを与えたいという思いがあったのかもしれない。実際、明確なテーマが見つからないまま写真を選んでいく中で、全体を通して感じられるフックが、空気や風のような見えないものを対象を通じて得られる感覚だと感じたことが、このタイトルをつけた理由だと記憶している。考えてみれば当たり前の理屈で、風景写真には風も空気も写っているから風の景=ありさまを写したものという意味になる。では風がなければ風景にはならないのか?などと考え、禅問答になりそうな、「なぜ風景写真なの?」という問いの先に、なかなか奥が見えないのは、とりとめのない風景写真という言葉に原因があることも実を言えば否定できない。相変わらず大仏の掌の上で空回りしていることになす術もなく年齢を重ねる日々だ。
鈴木さんに話した私の体験は以下の通りである。
子供時代、母の実家の向かいにあった神社を遊び場にしていた。お盆の夜には野外映画館になり、「大魔神」を観た記憶もある。ある日、勇気を出して神社の斜面を登り奥へ進むと、もう一つ神社が現れた。すり鉢状の場所にあるその神社の格子窓を覗くと、白い馬の彫像があり、見慣れない光景に不気味さや恐れを感じて慌てて山を下りた。しかし、その後再び訪れても、その神社は見つからず、狐につままれたような気持ちが残った。
もう一つは、少しいたずらをして叱られるのが怖くて家に帰れなくなった時のことだ。暗くなるまで裏の土手の桜の木に立てかけてあったハザ木の束の隙間に隠れて息を潜めていた。怖さのあまり時間の感覚がなくなり、外が暗くなると大人たちが私の名前を呼ぶ声が聞こえてきた。ついに我慢できず、こっそり家に戻り、姉にしがみついて泣いた。それが私の原体験のひとつでもある。
今と違い、当時は子供だけで危険な場所にも行けた時代で、そのまま戻らなかった子供も多かったのかもしれない。自分もよく今まで生き残ったものだと思うことがある。写真は未熟だったが、そうした思いが写真に表れているような気がする。説明はできないが、気分で撮っていたとしか言いようがない。しかし、この写真展が、良くも悪くも私の原点になったと今は感じている。
そんな話を聞いていただいた翌日か翌々日には、鈴木さんから詩が完成したとの連絡があった。私が語った断片的な体験から創作、見事に一編の物語が生まれていた。
「導かれて」鈴木良一 詩
私は導かれているのだと思う
子供の頃
それは小学校2年か3年の頃
導かれるかのように
山ふところへと誘われたことがある
両親や村人達は
”神かくし”にあったと
わたしを必死で捜したという
わたしが山から家へ帰り着いた時
口々に”神かくし”から戻った
奇跡が起こったと話しかけてきた
わたしにはそれが何を意味するか理解できなかった
かすり傷は負ってはいたものの
無事に帰ったわたしを喜びあっていたが
その喜びあいようは
尋常ではなかった
わたしには不思議な光景ですらあった
わたしは
現在(いま)は あの出来事を
「山野行」と名付けている
この出来事が、
三日間にも及ぶわたしの行方不明であり
”神かくし”されていた時間だという
この三日という時の経過も
そののち
ことあるごとに 母が
「お前が、三日もの間神かくしされてた時
母さんはどれほど心配したことか」
と、語りわたしに言い続けていたので
そう思い込もうとしているふしがある
なぜなら
わたしが「山野行」と名付け
母たちが”神かくし”と呼ぶ私の失踪は
わたしにとっては
ほんの一瞬の出来事だったという思いが強く
いつもの遊び場所から家に帰り着くまでの
十分にもみたない時間ではなかったかという
思いが強いからだろう
幼少期のいつもと変わらない夕暮れ
かくれんぼして
木の陰でオニを待っている
トキメク一瞬のようにしか
この出来事を思い出せないせいかも知れない
けれど
その瞬時にして垣間見た「山野行」
わたしの幻視したものの体感は
その後のわたしを深く規定し
わたしに迫ってくる
幻影というか
悪夢というか
あるいはここちよいものというか
私を導いて
何処へか向かわせる大きな力を
現在(いま)もわたしにふるっている(と感じられる)
わたしが「山野行」と名付け
母たちが”神かくし”と告げる出来事の
一部始終はともかく
その端緒は
わたしの記憶では
はっきりとした輪郭を持って思い出せる
川はいつもの瀬音を立てていた
山里の陽は 流れるように落ちる
その日わたしは一人だった
陽が落ち始め
川霧が立ち始めた
わたしは家へ帰ろうと
普段ならば 村うちの悪仲間(わるがき)と
三人、四人と連れ立って遊び呆けている
村社の
さらに奥まった場所(ところ)にある
すり鉢状の底の広場から家へと歩き出した
そこは、おとなしい子はめったに近ずかない
なにか秘密めいた場所であり
後年に知ったことだが、ここは
かつては若衆宿という
村落の共同体を確認する小屋が
かけられていたところだという
この日の川霧は 強く 濃く流れ
わたしを襲うかのように感じられた
何かに飲みこまれてゆくかのようにさえ思えた
それでも
遊びなれた草木を手探ぐりしながら
確実に 家への道を進んでいた(つもりだった)
村社の破れかけた裏戸も
側面にビッシリと貼られた絵馬の
かすかに残る原色をもわたしは見ている
いつもと少し違っていたとすれば
すでに陽は
山の端へ落ちている時刻なのに
わたしが日頃、あんな馬に一度乗ってみたいと
気に入っていた一枚の絵馬を見あげると
そこへ一筋の光の束が差しかけており
絵馬の眼が
ひときわなつかしそうに
わたしを見返した(ことぐらいだった)
その時まで
聞こえていた
瀬音が絶え
馬の嘶きが
耳元で聴こえた
と
思うと
わたしは
絵馬とみまごう
白い馬の背に
くわえ あげられ
裸馬の
背で
振り落とされまいと
必死で
立髪をにぎりしめていた
けれど馬は
あばれる様子もなく
ゆっくりと
乳白色の 川霧の中
村社の鳥居をくぐり
村里へ下る
苔むした石段を
蹄を響かせて下り始めていた
わたしは
驚くより 安堵し
すぐ夕食の待つ家へ
帰り着くと
確信した
そして
わたしは
家へ着いた
騒ぎたてる人々の前に居た
わたしの「山野行」として思いだされるのは
これだけである
わたしが 家へ帰り着いた時の
村中の騒ぎは尋常ではなかったが
わたしには
喉の渇きもなかったし
空腹感すら覚えていなかった
いつも
わたしを導くかのように
襲ってくる名状しがたい力とは
この「山野行」の記憶から
乳白色の川霧であり
絵馬にさ差しかかる一束の光であり
それら全体を包む
朽ちてゆくものの意志といったようなもの
こうしている今も
わたしに力をふるっていると感じられる
けれど
これらの出来事を現実にわたしが引き起こし
村中を騒ぎたてさせ
母に人かたならぬ心配をかけるほどの
出来事であったかどうか
わたしには
今も
判然と
しないのである